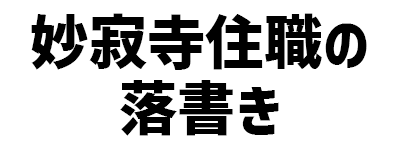お寺は誰のものなのでしょうか?住職である私の思いを書きたいと思います。
檀家制度とは
まずは、檀家制度から考えなくてはなりません。
檀家制度(だんかせいど)とは、寺院が檀家の葬祭供養を独占的に執り行なうことを条件に結ばれた、寺と檀家の関係をいう。寺請制度(てらうけせいど)、あるいは寺檀制度(じだんせいど)ともいう。江戸幕府の宗教統制政策から生まれた制度であり、家や祖先崇拝の側面を強く持つ。
平たく言えば、お寺がそれぞれのおうちのご葬儀やご法事を責任を持って勤めるかわりに、檀家のおうちはそのお寺を支えていくという制度です。互助関係にあるということですね。
檀家制度はいらない?
昨今はこの檀家制度そのものを否定し、個人で宗教を選ぶ時代だと声高々に叫ぶお坊さんもいらっしゃいますが、檀家制度と個人で宗教を選ぶことは別の話です。
なぜなら個人で宗教を選ぶことは当たり前だからです。檀家制度自体が個人で宗教を選ぶことを阻んでいるのではなく、檀家制度を当たり前と思う習慣や道徳観、はたまた一部のお坊さんが宗教を選ぶことを阻んでいるからです。檀家制度が互助関係を持てない状況になっているのなら、とっくにその制度は形なく崩壊しているはずです。ですが、現在も檀家制度があり続けるのはある程度の互助関係を保っているからです。
私のお預かりするお寺でも、檀家を離れられる方もおられます。様々な理由がありますが、私はお止めしません。檀家制度に関わらず宗教を選べばいいのです。しかしながら現実に離れることを執拗に止めるお坊さんもいることを否定することはできません。
お寺は誰のもの?
さて、本題に戻りますが、お寺は誰のものか。お寺は檀家の皆様の共有物だと思います。住職一人のものではありません。住職は「住する職」ですから檀家の皆様の共有物であるお寺を住みながら護っているということです。
双方に勘違いしてはいけないと思うのが、みんなのものであり個人のものではないということです。お坊さんは檀家さんに、檀家さんはお坊さんにそれぞれ敬意を払うべきですし、それぞれ払われるべき生き方をすべきだと思います。残念ながらお坊さんにも上から目線の方はたくさんおられます。これを読んでくださる方にもそう思う方はいらっしゃるでしょう。これから檀家さんとお坊さんが素晴らしい関係になっていくことを心から念じております。